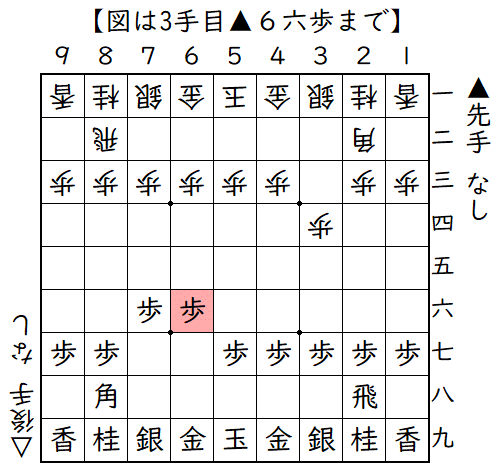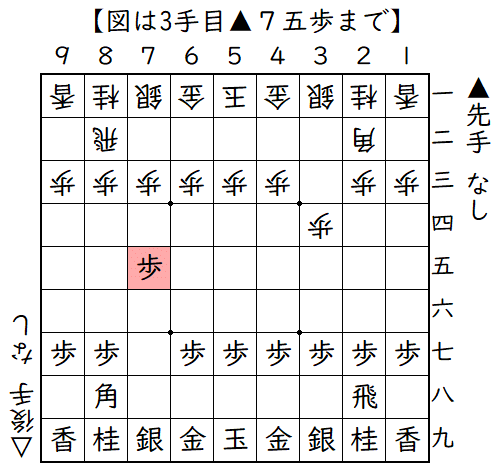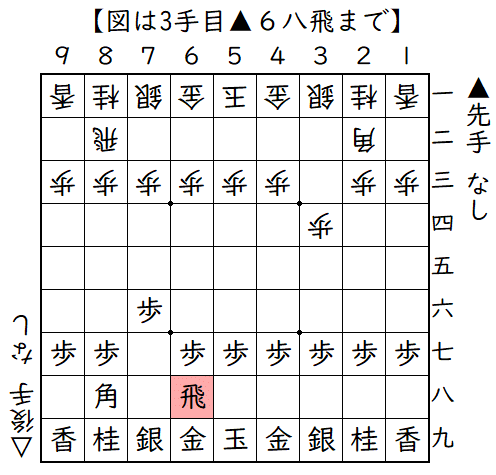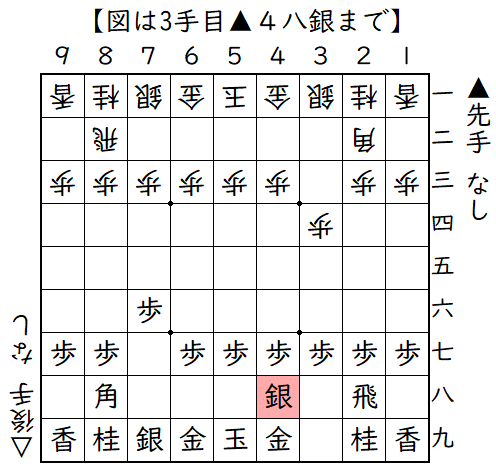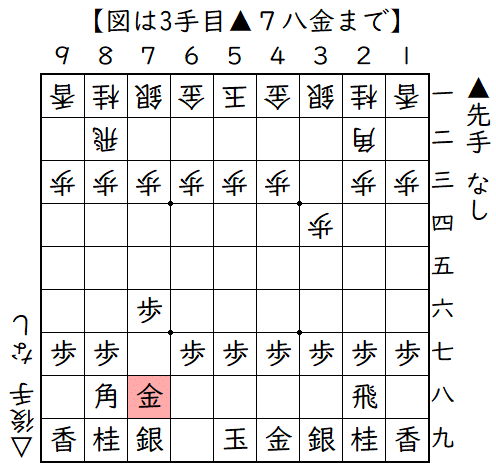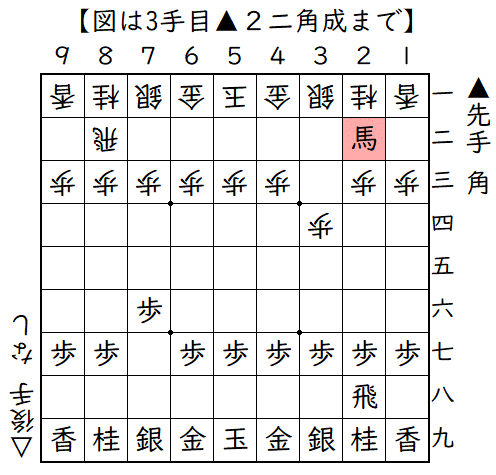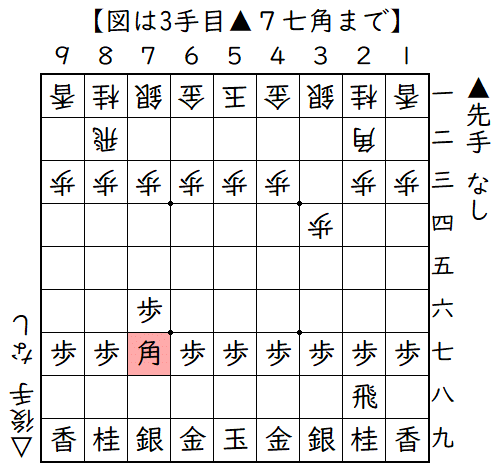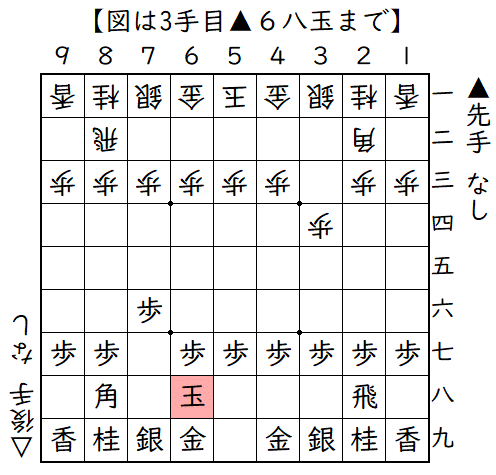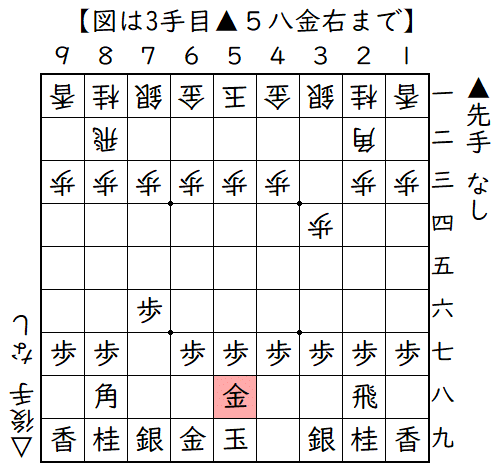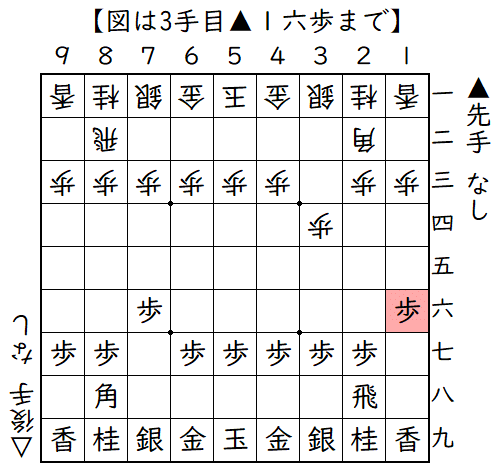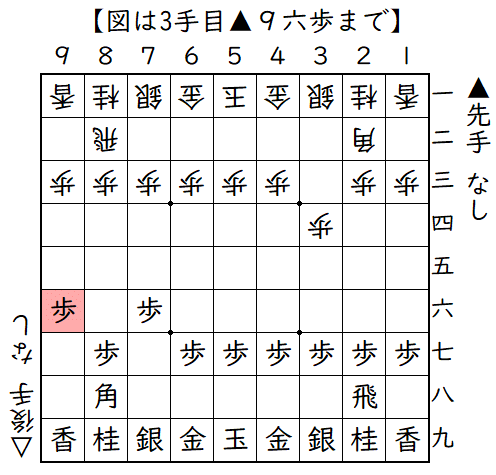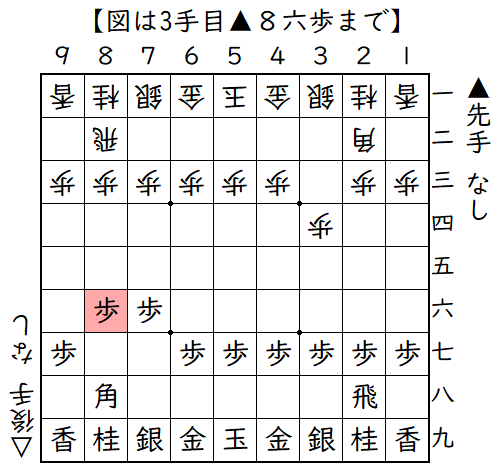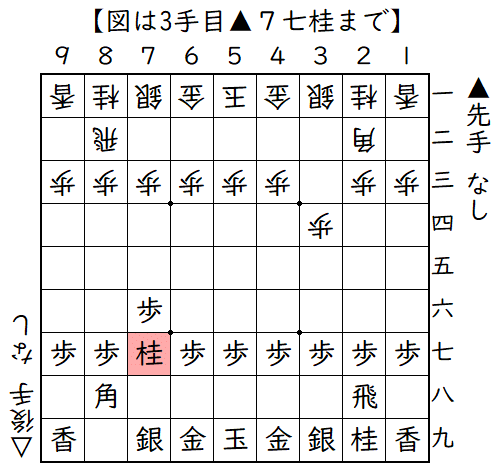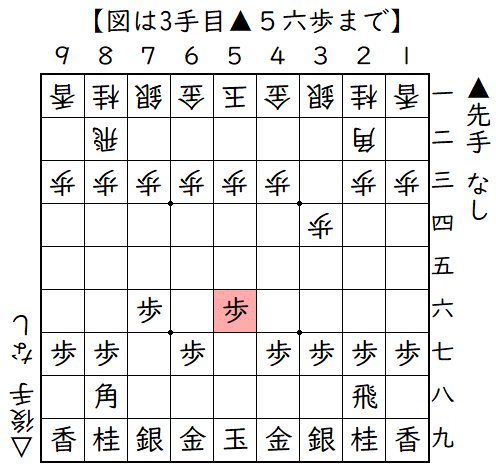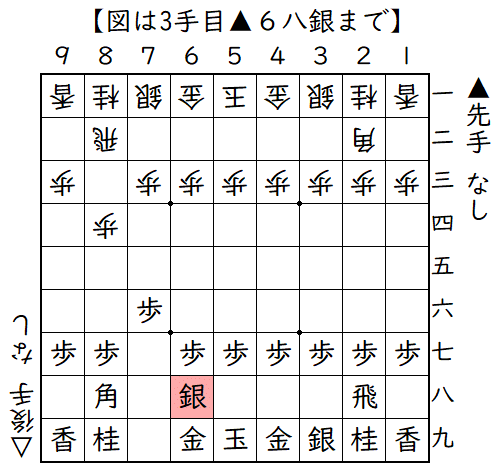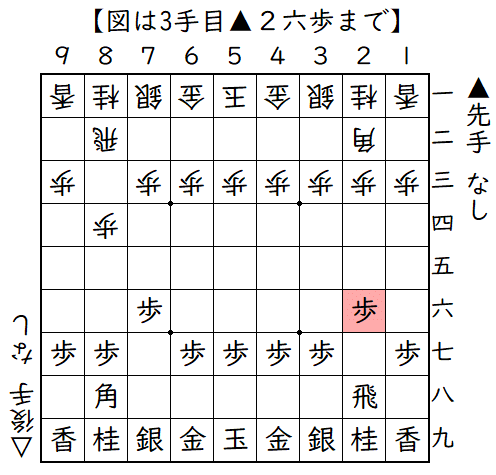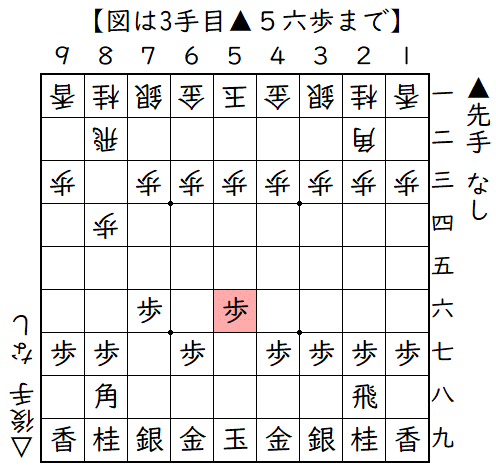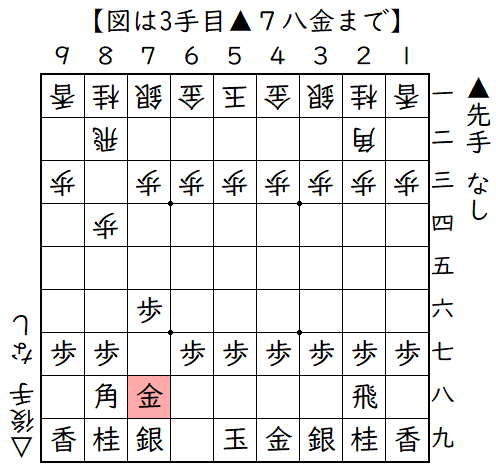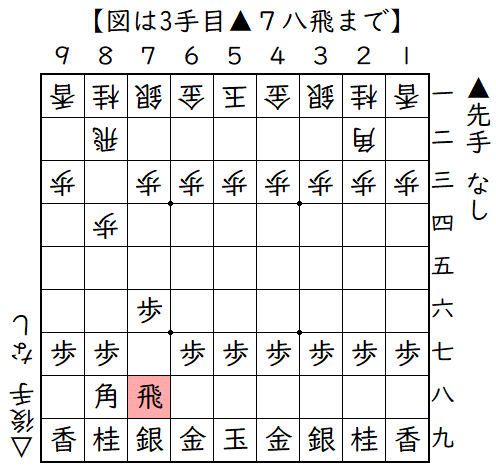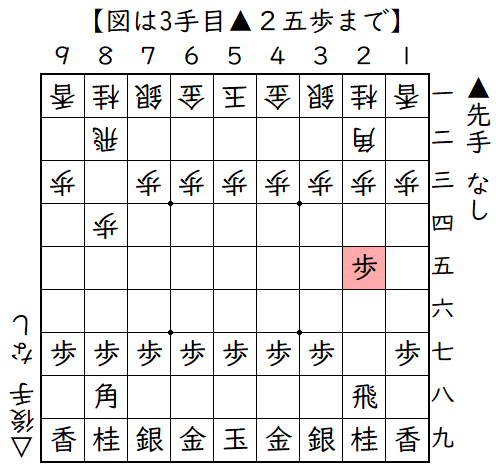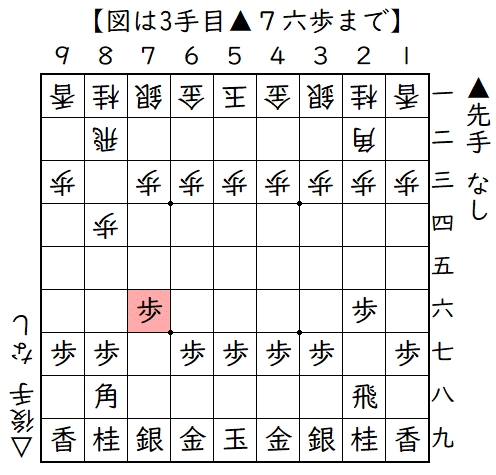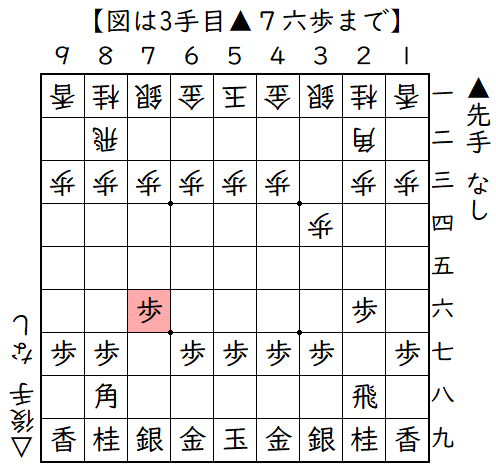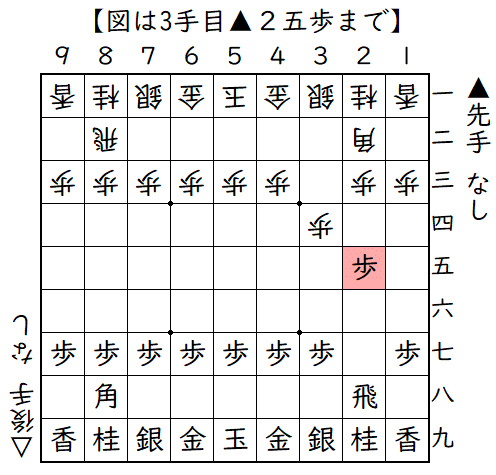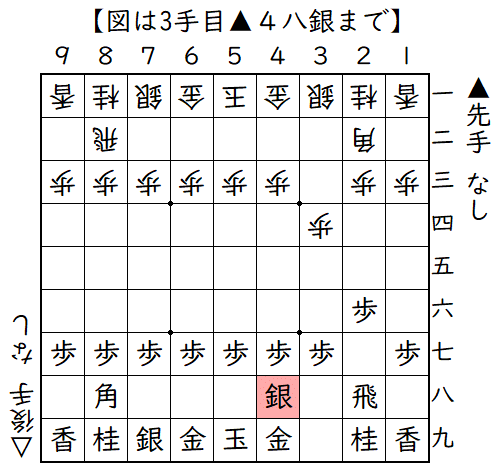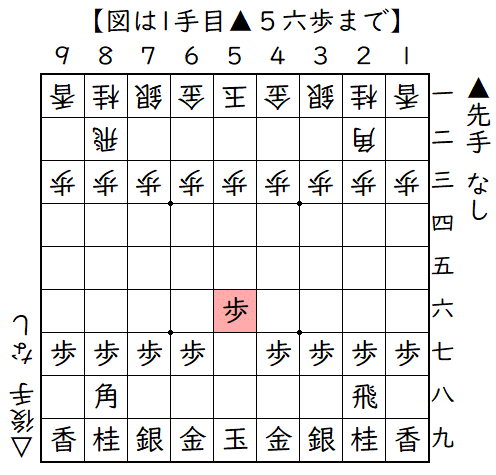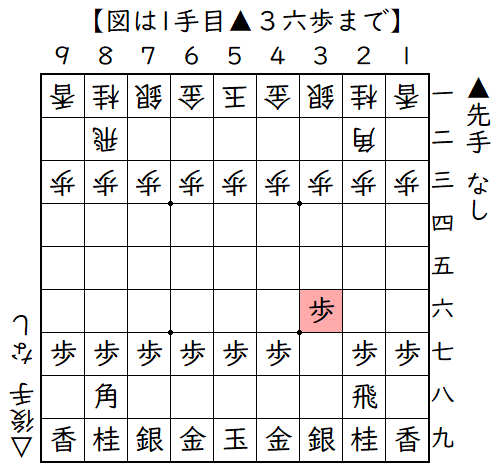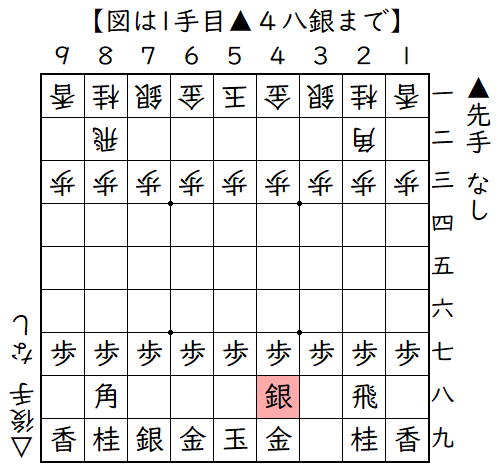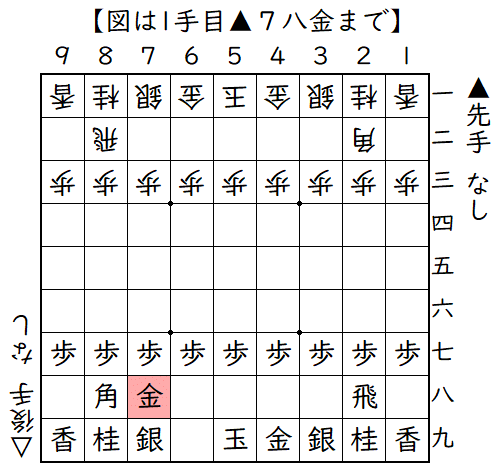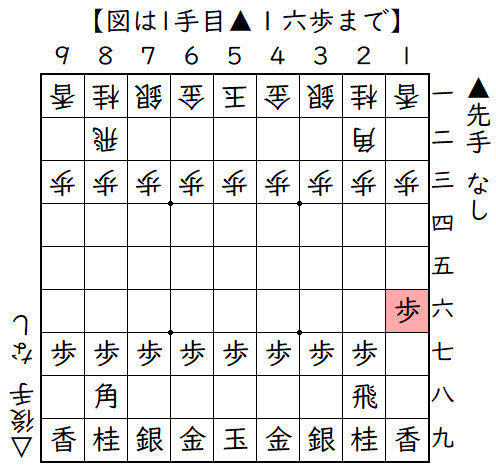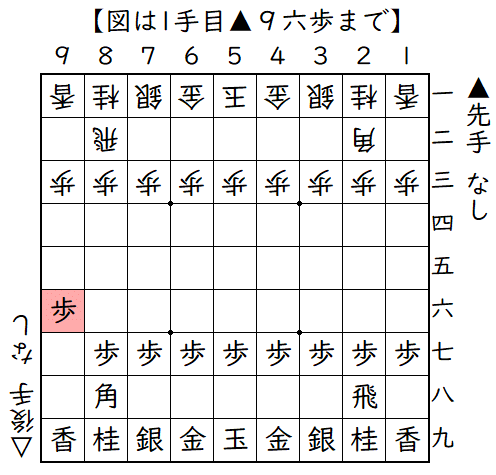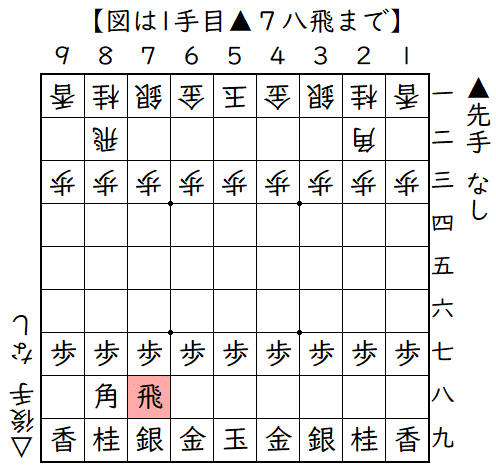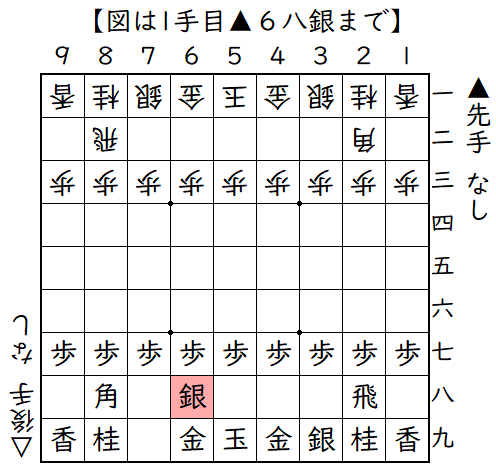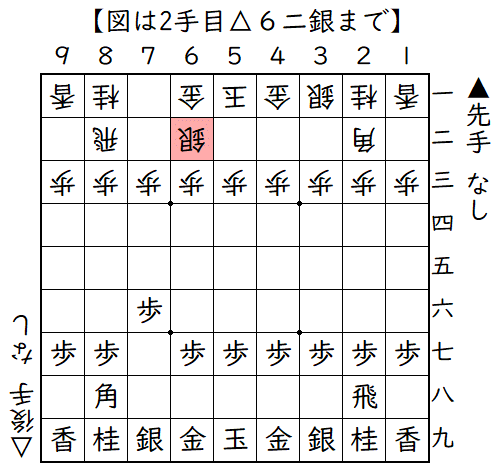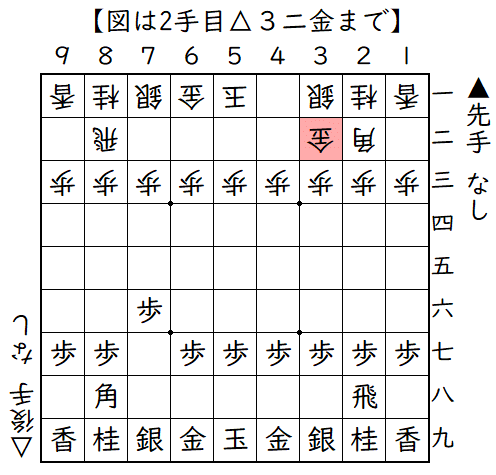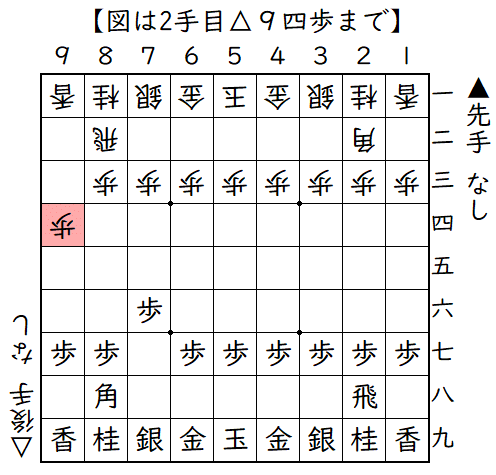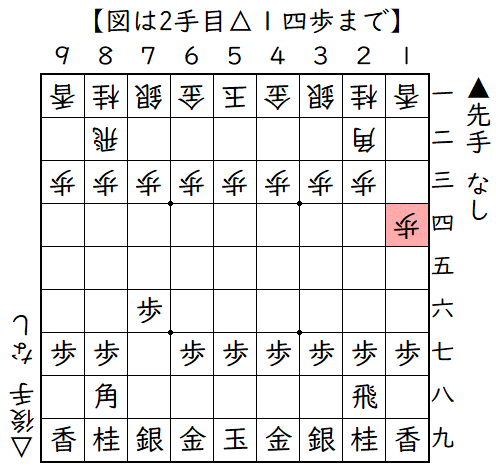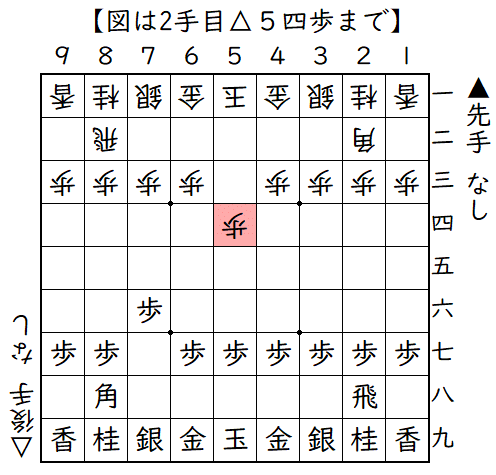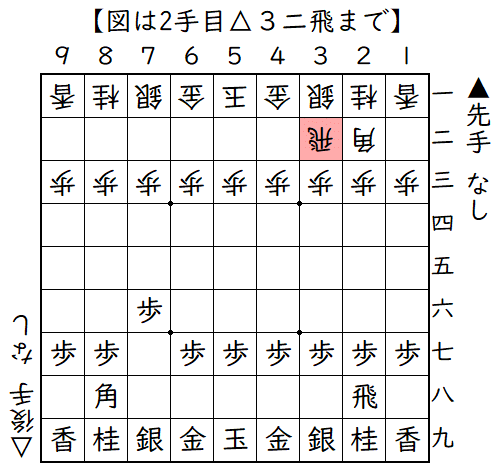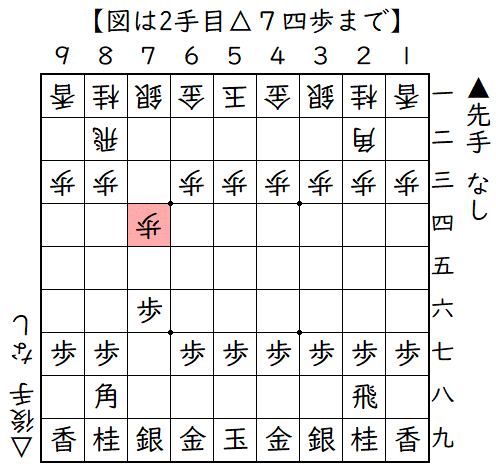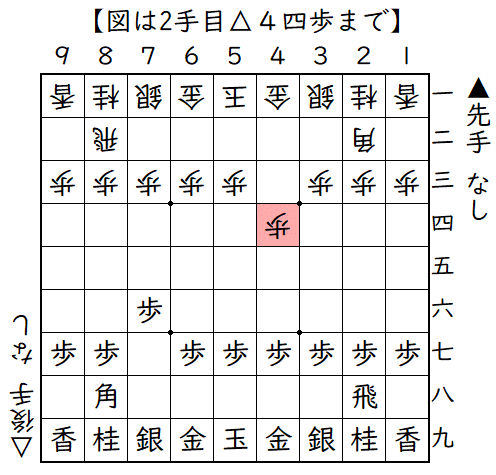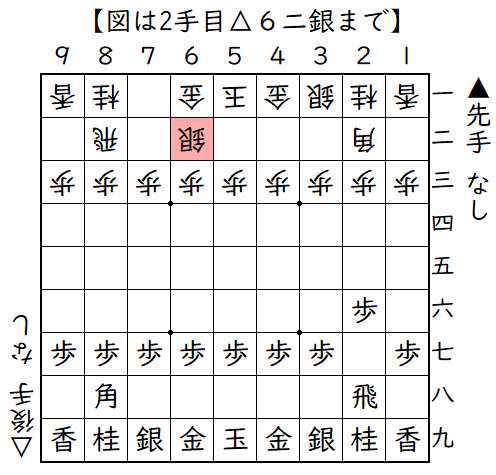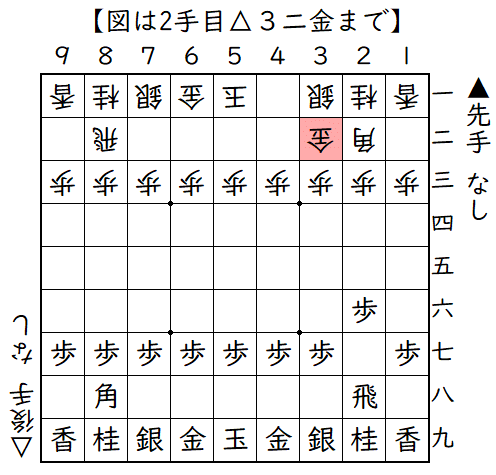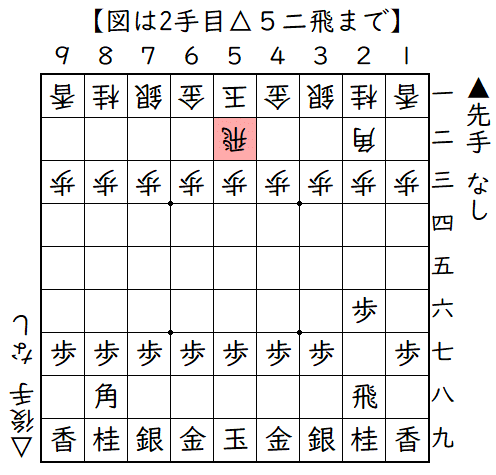1手目 |
2手目 |
3手目 |
4手目 |
戦型 |
▲7六歩 |
△3四歩 |
▲2六歩 |
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△8四歩
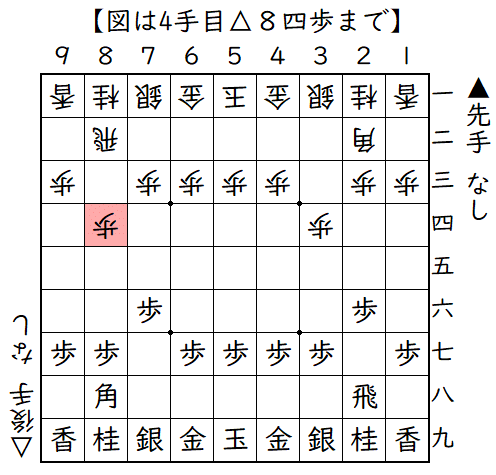 横歩取りの出だし。後手次第で一手損角換わりに進むこともある。
横歩取りの出だし。後手次第で一手損角換わりに進むこともある。
先手がそれらの戦型を避けて矢倉や陽動振り飛車にすることもあるので、考えるだけならまだ何にでもなる。
-
(1)▲2五歩と飛車先を伸ばす手が自然。
-
(a)△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△8六歩▲同歩△同飛▲3四飛で横歩取りか、
-
(b)△3二金▲7八金△8八角成▲同銀△2二銀で一手損角換わりか。
-
(2)▲7八金と待つと△3二金▲2五歩に、
-
(a)△8五歩で横歩取りか、
-
(b)△8八角成で一手損角換わりかを後手が選ぶ。
-
どちらも嫌なら、
(3)▲6六歩と突き、△8五歩▲7七角△3二銀▲8八銀△6二銀▲2五歩△3三銀▲6八角の先手無理矢理矢倉や、雁木、陽動振り飛車も考えられる。
横歩取り、相掛かり、一手損角換わり、矢倉、対抗形
|
戦型未確定 |
△3二金 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△3二金
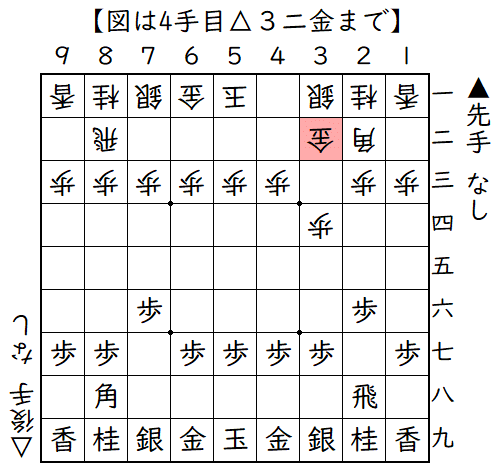 一手損角換わりの出だし。△8四歩型と飛車先不突型の選択ができる。また、横歩取りを誘うこともできる。
一手損角換わりの出だし。△8四歩型と飛車先不突型の選択ができる。また、横歩取りを誘うこともできる。
-
(1)▲2五歩には、
-
(a)△8八角成で飛車先不突の一手損角換わりに出来る。
-
(b)△8四歩▲7八金△8八角成なら△8四歩型の一手損角換わり。ただし先手には、▲7八金のところで▲2四歩△同歩▲同飛の権利があり、それだと横歩取りや相掛かり系の将棋になる。
-
(2)▲7八金には、
-
(a)△8八角成なら飛車先不突型の一手損角換わり、
-
(b)△8四歩と一旦突いておき、▲2五歩に△8八角成なら△8四歩型の一手損角換わり。
-
(c)△4四歩と突き無理矢理矢倉や雁木、振り飛車にも出来る。
一手損角換わり、横歩取り、相掛かり、矢倉、対抗形
|
戦型未確定 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩
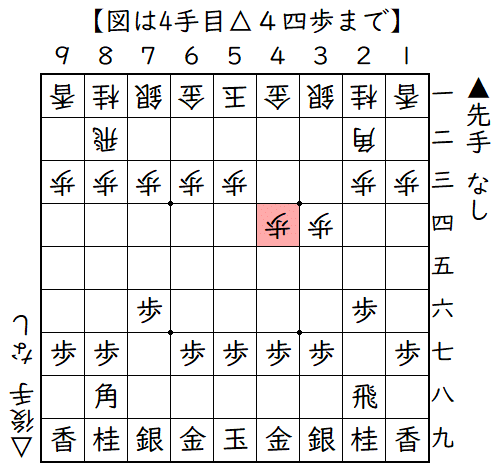 角道を止める穏便な指し方。後手は作戦を矢倉や雁木、または振り飛車に絞る。
角道を止める穏便な指し方。後手は作戦を矢倉や雁木、または振り飛車に絞る。
ここで▲2五歩△3三角の交換を入れるかどうかが、先手のひとつの悩みどころ。
-
(1)▲2五歩△3三角としておけば、後手が矢倉に組む(△3三銀型を作る)には手数が必要となる。一方で、後手が雁木や振り飛車にするつもりなら特段気にする手でもない。また△2四歩と反撃しやすくなるため後手の向かい飛車を誘発することもある。
-
(2)▲4八銀のように▲2五歩△3三角を決めない手を指すと、△4二銀でスムーズに矢倉に組まれる可能性がある。
対抗形、矢倉、居飛車力戦
|
矢倉 |
対抗形 |
居飛車力戦 |
△5四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△5四歩
ゴキゲン中飛車の出だし。
以下、
-
(1)▲2五歩(▲4八銀)に△5二飛で準備完了。
先手の作戦は様々。超速▲3七銀、玉を堅くできる丸山ワクチン+佐藤流、派手な変化の▲5八金右超急戦が有名だが、舟囲いでの急戦や、穴熊もある。
-
(2)▲2二角成△同飛▲5三角は△4二角で無効。この手が通らないので△5二飛が成立する。
対抗形、居飛車力戦
|
対抗形 |
居飛車力戦 |
△4二飛 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△4二飛
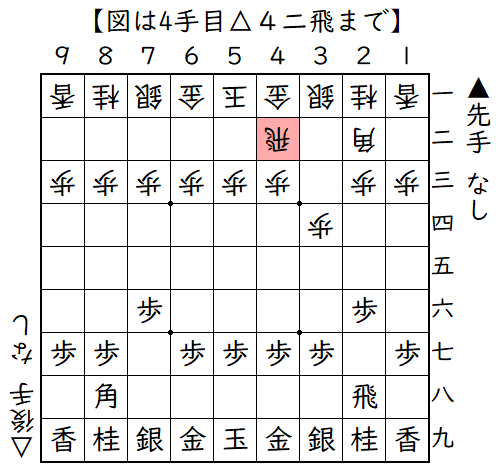 角交換四間飛車の出だし。
角交換四間飛車の出だし。
後手が角道を開けたまま飛車を振るなら、▲2二角成~▲6五角の筋がない4二が無難。
基本は▲6八玉に△8八角成▲同銀と決めてしまい、先手に居飛穴を組みにくくさせて戦う。また、先に片美濃囲いに囲ってしまい、それから△3二飛と振り直す4→3戦法もある。角道を止めてノーマル四間飛車に戻してもよい。
対抗形
|
対抗形 |
△8八角成 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△8八角成
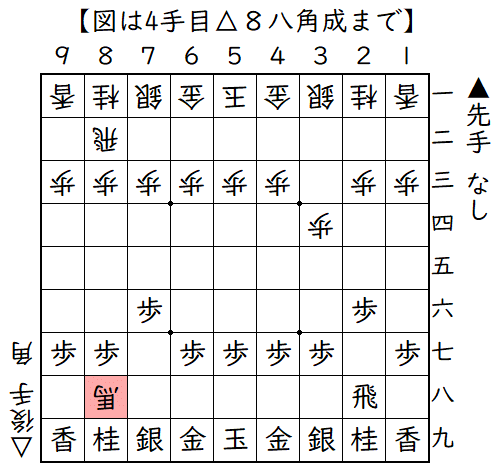 4手目にして角交換。
4手目にして角交換。
▲8八同銀と取ったところで、
-
(1)△2二銀▲2五歩△3三銀▲4八銀が進行の一例。そこで、
-
(a)△7二銀~△6四歩の一手損角換わりか、
-
(b)△4二飛や(c)△2二飛で角交換振り飛車にするか。
-
(2)△6五角と筋違い角を打つ手も考えられる。ただ、ほとんど指されない。
角換わり、対抗形
|
角換わり |
対抗形 |
△3三角 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△3三角
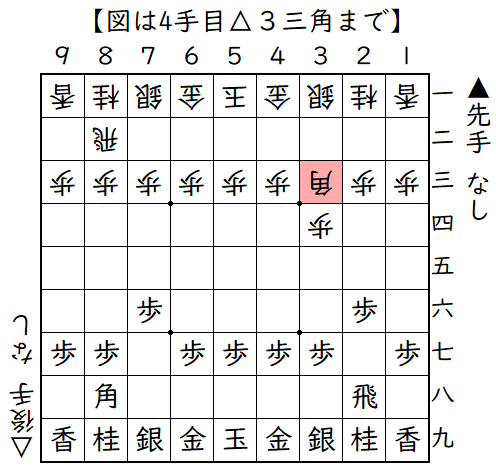 4手目△3三角戦法の出だし。
4手目△3三角戦法の出だし。
2008年度の後手番勝ち越しに一役買った出だしであるが、現在は愛好家がたまに指すくらい。
振り飛車党のみならず居飛車党もこの手を指しており、作戦が広い。
基本的には▲3三角成△同桂と進み、そこから後手の狙いはダイレクトに△2二飛と向かい飛車に振る順。すぐ△3二金と上がって居飛車で指す展開もある。
対抗形、角換わり、居飛車力戦
|
対抗形 |
角換わり |
居飛車力戦 |
△3五歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△3五歩
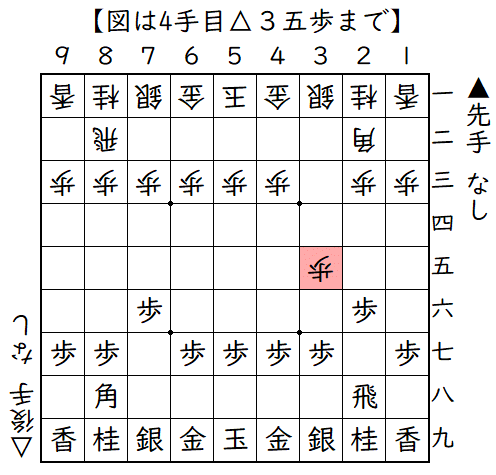 後手早石田の出だし。
後手早石田の出だし。
-
(1)▲2五歩△3二飛▲6八玉△6二玉に▲2二角成~▲6五角が成立するとプロでは結論付けられており、プロにおいては無理筋となっている。
-
また、早石田封じで有名な手として、
(2)▲6八玉、
-
(3)▲5六歩という手がある。
これらの手に△3二飛だと▲2二角成△同銀▲6五角の筋がある。そのため一旦△4四歩や△4二飛としなければならず、駒組みに制限がある。
対抗形
|
対抗形 |
居飛車力戦 |
△9四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△9四歩
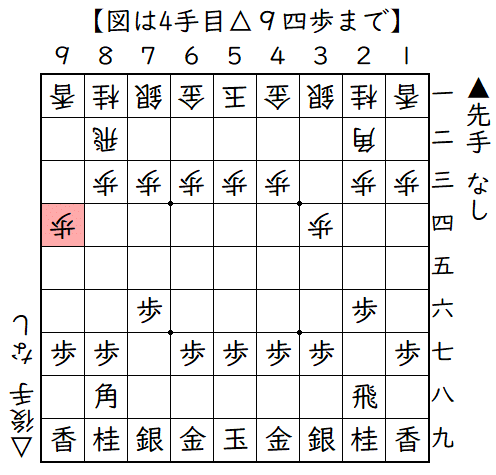 端歩で様子見。一手損角換わりや角交換振り飛車を狙っている。
端歩で様子見。一手損角換わりや角交換振り飛車を狙っている。
後手玉が9筋側に逃げる形になった際、玉が広い。先手の居飛穴に対する端攻めの狙いにもなっている。▲2五歩と突かれたときはまず角交換するつもりであることが多いが、全体的にはまだ戦型は決められない。
戦型未確定
|
戦型未確定 |
△1四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△1四歩
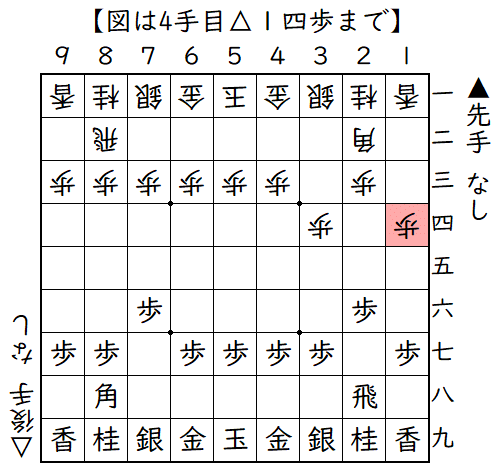 端の様子見。狙うとすれば一手損角換わり。
端の様子見。狙うとすれば一手損角換わり。
これも▲2五歩と突かれたら一手損角換わりにするつもりであることが多いが、まだ決まらない。
戦型未確定
|
戦型未確定 |
△6二銀 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△6二銀
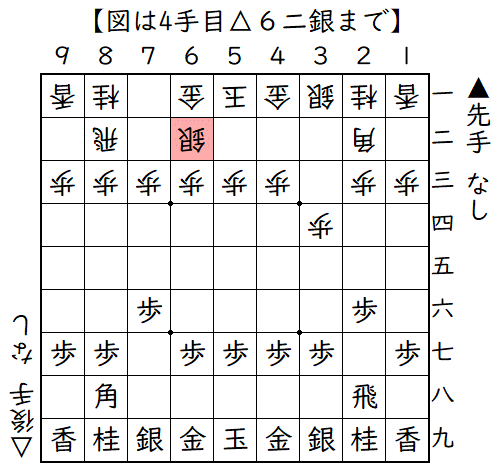 △6二銀は普通の手のように見えて、全然そうではない。
△6二銀は普通の手のように見えて、全然そうではない。
以下▲2五歩に、
- 一手損角換わりのつもりで
(1)△8八角成▲同銀△2二銀とする手には、▲2四歩△同歩▲同飛のときに2二の銀に紐が付いていないため、△3二金▲2八飛と一方的に飛車先を交換させるしかない。
-
なのでそもそも
(2)△3二金と上がり、先手に2筋を切らせて指すほうが無難。
-
なお、上級編として
(3)△7四歩と言う手もある。▲2四歩△同歩▲同飛に、▲2三飛成を受けない△7三銀が定跡。以下▲2三飛成に△8八角成▲同銀△2二飛とぶつけて指す。用法・用量に注意。
居飛車力戦
|
居飛車力戦 |
△7四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△7四歩
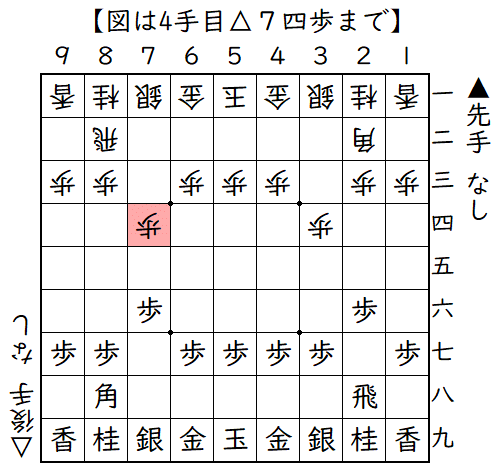 2手目△7四歩戦法の変形。
2手目△7四歩戦法の変形。
以下▲2五歩△7二飛▲7八金△3二金と進んで力戦にするのが狙い。
居飛車力戦
|
居飛車力戦 |
△3三桂 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△3三桂
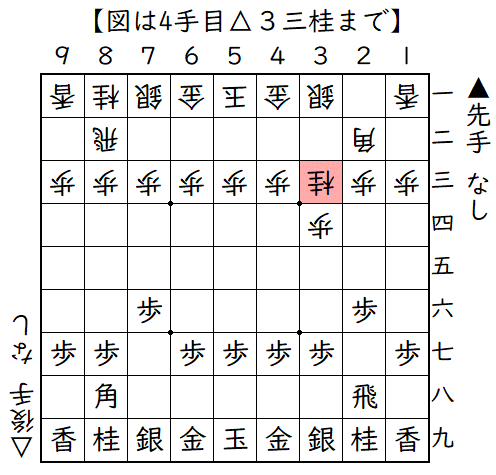 後手鬼殺し戦法。
後手鬼殺し戦法。
以下▲2五歩に△4五桂と跳ね、▲4八銀△3五歩▲4六歩△8八角成▲同銀△5五角と攻め、▲7七銀△4六角▲5八金右に△3六歩と3七めがけて殺到。以下▲4七金に△3二飛と角を見捨てる手が必殺で、▲4六金△3七歩成▲同桂△同桂成▲同銀△同飛成で鬼殺し大成功!
…と思いきや、そこで▲1五角の王手竜があって実は大失敗。速攻を狙うには何かしら相手をごまかす必要がある。
鬼殺し
|
奇襲戦法 |
△2四歩 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△2四歩
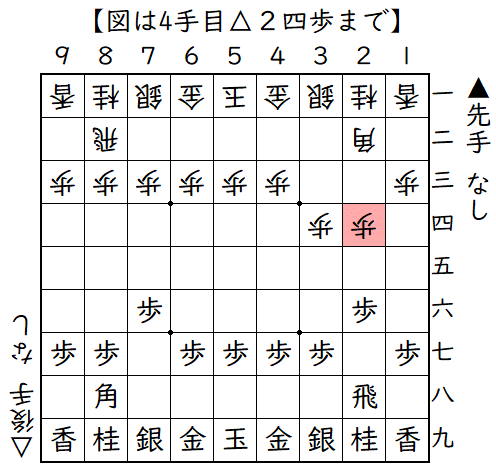 後手角頭歩戦法。
後手角頭歩戦法。
▲2五歩△同歩▲同飛としてきたら、△8八角成▲同銀と角交換する。以下、
-
(1)△3三桂と跳ねる手と、
-
(2)△2二飛とぶつける手に分かれる。
角頭歩戦法
|
奇襲戦法 |
△3二飛 |
▲7六歩△3四歩▲2六歩△3二飛
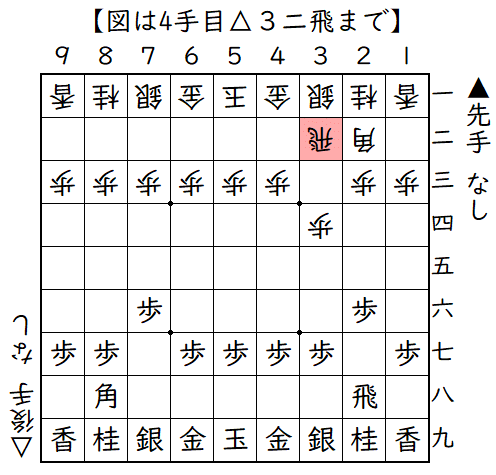 菅井流4手目△3二飛。
菅井流4手目△3二飛。
▲2二角成には△同飛と取り、▲6五角△7四角▲4三角成△4二金▲3四馬△4七角成が一例。
対抗形
|
対抗形 |
1手目 |
2手目 |
3手目 |
4手目 |
戦型 |
▲7六歩 |
△3四歩 |
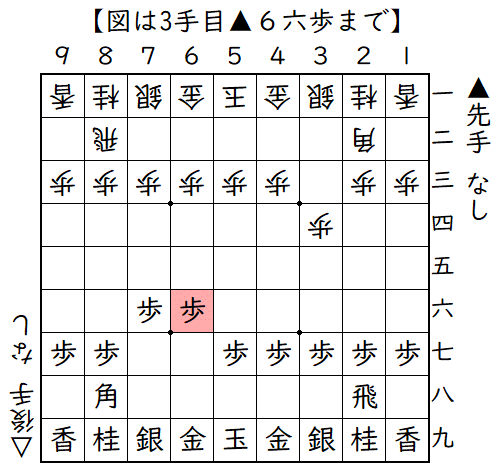
▲6六歩
先手から角道を止める順。
居飛車を指すつもりでこの歩を突くと、後手が飛車を振った際に作戦を狭まるので、基本的には先手振り飛車模様と捉える局面。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△8四歩
後手が居飛車を明らかにする。
-
(1)▲6八銀と指すと、矢倉の出だし(▲7六歩△8四歩▲6八銀△3四歩)で5手目▲6六歩と突いたのと同じ局面になる。この順を、専門的にはウソ矢倉と呼ぶ。
-
(2)▲6八飛、(3)▲7八飛など、先手が飛車を振れば対抗形になる。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△6二銀 |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△6二銀
後手が飛車先を保留した順。
-
(1)▲6八銀でウソ矢倉もあるが、それだと後手が飛車先不突なのでその一手を他のところに回せてやや得している。
-
それでも矢倉をやりたければ、
(2)▲5八金右のほうが、後手が右四間に来たときに有力と考えられている。
-
(3)▲7八飛と指せば、そこから△8四歩でも▲7五歩△8五歩▲7六飛と出来るので、石田流本組に組める。上のウソ矢倉の順と、この順を組み合わせて3手目に▲6六歩と指す作戦がある。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△3五歩(△3二飛) |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△3五歩
後手三間飛車で、相振り飛車模様。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
△3三角 |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△3三角
相振りの△3三角戦法で、角道を開けたまま向かい飛車に振るのが狙い。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△4四歩
お互い角道を止めあってお堅い順。
相振り飛車、対抗形、矢倉
|
相振り飛車 |
対抗形 |
矢倉 |
△5四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△5四歩
相振り飛車模様で、△4二銀~△5三銀としてから飛車を振ろうとしている。
相振り飛車、対抗形、矢倉
|
相振り飛車 |
対抗形 |
矢倉 |
△4四角 |
▲7六歩△3四歩▲6六歩△4四角
相振り△3三角戦法の親戚のような感じ。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
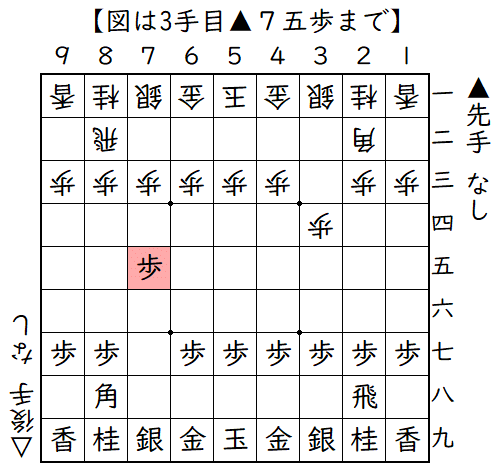
▲7五歩
先手石田流の狙い。
2手目△3四歩に対する振り飛車先手番の作戦として有力。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△8四歩
先手早石田に対して、最も強い態度で臨む手。
こうなったら▲7八飛に△8五歩と伸ばすしかなく、先手も後手も勇気が必要な局面になる。
対抗形
|
対抗形 |
△4二玉 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△4二玉
早石田封じ・その1。先手早石田に対して、穏便な態度で臨む。
-
(1)▲7八飛なら△8八角成~△6五角が狙い。
-
したがって先手は
(2)▲6六歩と止めてから飛車を振ることが多い。
-
また、△4二玉を見て
(3)▲2六歩と突き居飛車に持ち込む手もある。
対抗形、居飛車力戦
|
対抗形 |
居飛車力戦 |
△5四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△5四歩
早石田封じ・その2。先手早石田に対して、穏便な態度で臨む。やや相振り模様。
-
(1)▲7八飛なら△8八角成~△6五角に▲8五角と打ち返す。
-
したがってこちらも
(2)▲6六歩と角道を止めてから飛車を振ることが多い。
対抗形、相振り飛車、居飛車力戦
|
対抗形 |
相振り飛車 |
居飛車力戦 |
△6二銀 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△6二銀
穏便な手。一応▲7八飛と指せるが、次に△4二玉と上がられたら▲6六歩なので、先に▲6六歩と突くことも多い。
対抗形、相振り飛車
|
対抗形 |
相振り飛車 |
△8八角成 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△8八角成
石田流封じと呼ばれる手。
-
(1)▲8八同飛なら△4五角と打つ。▲7六角は手筋の切り返しだが△4二玉と上がって受け、そこで先手が▲3八銀か▲3八金かという将棋になる。
-
(2)▲8八同銀もあり、その場合は△4五角が打てないので駒組みになる。
対抗形
|
対抗形 |
相振り飛車 |
居飛車力戦 |
△3五歩 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△3五歩
相三間飛車。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7五歩△4四歩
後手が角道を止め、穏便な進行を望んだ順。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
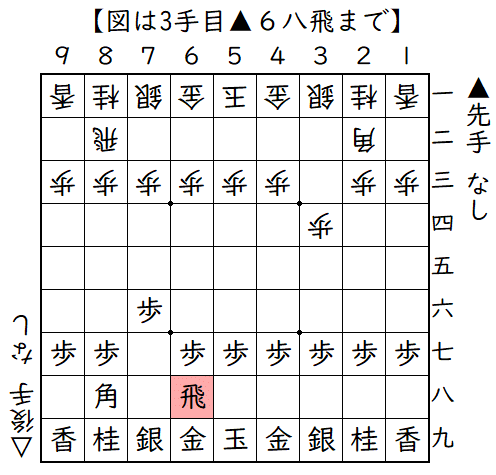
▲6八飛
先手の角交換四間飛車。
後手が居飛車の場合は後手番で指す際とあまり違いはないが、振り飛車の可能性があるため相振り対策が必要。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△8四歩
後手居飛車。先手は▲4八玉から角道を開けたまま駒組みするか、▲6六歩でノーマル四間飛車に戻すか。
対抗形
|
対抗形 |
△4二玉 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△4二玉
後手居飛車。この局面ではすぐに▲2二角成△同銀を決めるか、決めずに▲4八玉と上がって指すか、▲6六歩と止めて指すか。
対抗形
|
対抗形 |
△4二飛 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△4二飛
鏡指し。
相振り飛車
|
相振り飛車 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△4四歩
後手が角交換を避けて指そうと言う順。先手は▲6六歩~▲6五歩と伸ばすのが有力。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
△3五歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△3五歩
後手三間飛車で、相振り飛車模様。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
△3二飛 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△3二飛
4手目△3五歩同様、後手三間飛車で相振り。先に飛車を振った分、先手には▲2二角成~▲6五角の仕掛けがある。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
△2四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△2四歩
相振りのダイレクト向かい飛車。
以下△2五歩と先に伸ばし、タイミングを計って△8八角成~△2二飛と向かい飛車に振ろうと言う順。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
△1四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八飛△1四歩
端を打診。先手の基本思想は、対抗形になるなら受けたい、相振りになるなら受けたくない。それと相手の顔を見て、受けるかどうかを決めることになる。
相振り飛車、対抗形
|
相振り飛車 |
対抗形 |
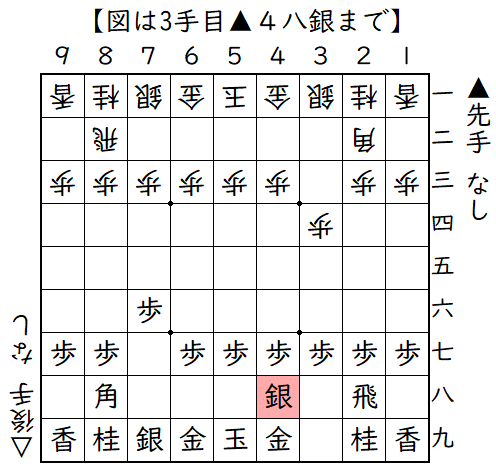
▲4八銀
アマチュア・ネットでは有名な英春流の手順。一般的には△8四歩と突かれたら飛車先の交換を防ぎづらく、後手が得しているとされる。その為、振り飛車党に対する「居飛車を指してみろ」と言う挑発の意味もある。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲4八銀△8四歩
-
(1)▲5六歩△8五歩▲5七銀と進め、△8六歩▲同歩△同銀と来たら▲2二角成△同銀▲7七角と打ちます、と言うのが英春流の基本定跡。
-
(2)▲6六歩と突き、
-
(a)△6二銀▲6八銀で矢倉。
-
矢倉党なら上のように進んでくれるといいだろうが世間は厳しく、
(b)△8五歩▲7七角と決められて無理矢理矢倉のコースに進むことが多い。
対抗形、居飛車力戦
|
対抗形 |
居飛車力戦 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲4八銀△4四歩
先手の突っ張った手に対して後手が穏便に済ませようとした順。後手の作戦は振り飛車か矢倉だが、どちらでも飛車先不突で右四間飛車を狙われる。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△3二金 |
▲7六歩△3四歩▲4八銀△3二金
8筋を交換すると想定される、来るべき決戦の前に備える指し方。
居飛車力戦、矢倉
|
居飛車力戦 |
矢倉 |
△3五歩 |
▲7六歩△3四歩▲4八銀△3五歩
後手石田流を目指す手。棒金が天敵。
対抗形
|
対抗形 |
△5四歩 |
▲7六歩△3四歩▲4八銀△5四歩
後手中飛車を目指す手。▲2二角成△同銀▲5三角は、▲4八銀が飛車の横利きを止めているため、△5五角で香取りが受からない。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
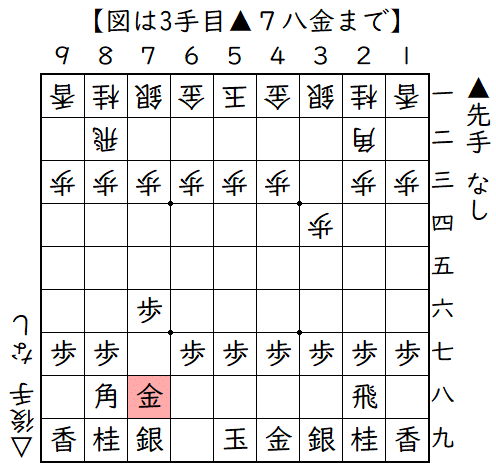
▲7八金
▲6八玉~▲7八玉の舟囲いを放棄し、居飛車党に対し「振り飛車にしてみろ」と言う挑発の意味がある。
|
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7八金△4四歩
角道を止めて穏便な指し方。ここから先手は、何が何でも右四間飛車と言う作戦がある。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7八金△8四歩
▲2六歩と突くと横歩取りの出だしから▲7八金と上がったのと同じ。他にも▲6六歩や▲6八銀など多々ある。
戦型未確定
|
戦型未確定 |
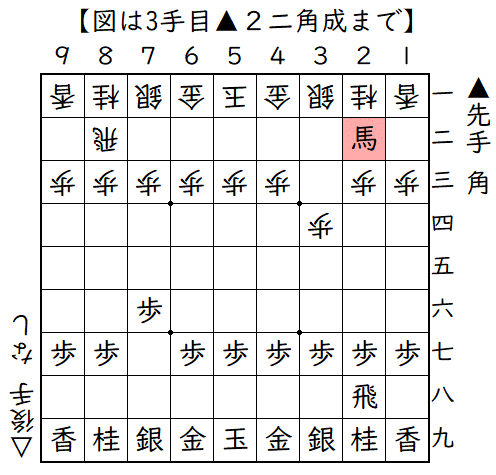
▲2二角成
いきなり角交換。
|
△同銀 |
▲7六歩△3四歩▲2二角成△同銀
▲2二角成は△同銀が普通。△同飛▲6五角△7四角▲4三角成△4二金▲3四馬△4七角成と言う進行も考えられるようになってきたが、ここでは割愛する。
このあとは、
-
(1)▲6五角と筋違い角を打つのが一例。
-
(a)△6二銀▲3四角△3二金、
-
(b)△5二金右▲3四角△6四歩の居飛車や、
-
(c)△6二飛▲3四角△4二飛で無理やり四間飛車にする手もある。
-
(2)▲6八銀や(3)▲8八銀と上がり、角を手持ちにしたまま駒組みにする順もある。角換わりか、角交換振り飛車かというところ。
筋違い角は後手番で2手目△3四歩と突く限りは避けようのない順なので、振り飛車党は対策が必須である。
筋違い角、角換わり
|
角換わり |
奇襲戦法 |
対抗形 |
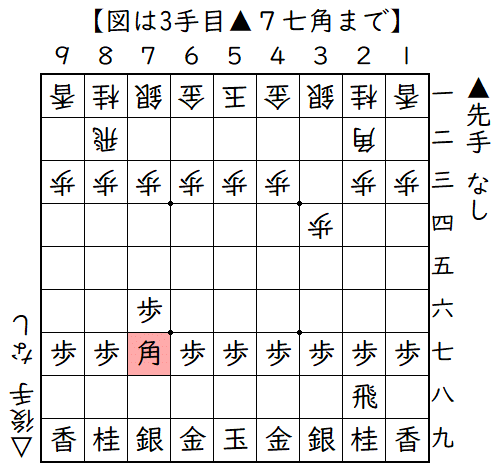
▲7七角
基本は△7七角成と取ってもらい、▲同桂と跳ねた形の駒組みを準備している。4手目△3三角の先手バージョンのようなもの。
|
△同角成 |
▲7六歩△3四歩▲7七角△同角成
▲7七同桂で一応狙い通りだが、桂頭を目標にされる恐れもある。
対抗形、角換わり、相振り飛車
|
対抗形 |
角換わり |
相振り飛車 |
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7七角△8四歩
後手が自重した順。
対抗形、角換わり
|
対抗形 |
角換わり |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7七角△4四歩
先手は角道を止めないまま駒組みが出来る。
対抗形、相振り飛車、矢倉
|
対抗形 |
相振り飛車 |
矢倉 |
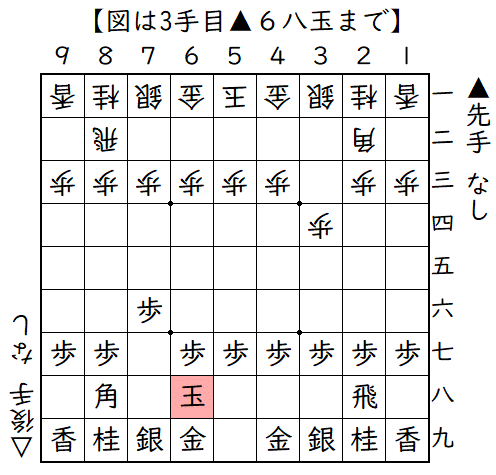
▲6八玉
▲6八玉は後手の振り飛車を決め打ちした手。特にゴキゲン中飛車を封じており、△5四歩と突くと▲2二角成~▲5三角で馬が出来る。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八玉△8四歩
△8四歩は後手が居飛車で咎めに行った順で、急戦矢倉などの進行になると、▲6八玉型は当たりが強い。
対抗形、居飛車力戦
|
対抗形 |
居飛車力戦 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八玉△4四歩
穏便な順。ここから対抗形になれば普通。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△3三角 |
▲7六歩△3四歩▲6八玉△3三角
4手目△3三角戦法の応用だが、既に▲6八玉と上がっているため、後手はダイレクトに△2二飛とは出来ない。
対抗形、矢倉、角換わり
|
対抗形 |
矢倉 |
角換わり |
△4二飛 |
▲7六歩△3四歩▲6八玉△4二飛
後手が飛車を振るとすれば▲2二角成~▲6五角のない△4二飛。
対抗形
|
対抗形 |
△5四歩 |
▲7六歩△3四歩▲6八玉△5四歩
△5四歩なら、▲2二角成△同銀▲5三角で馬の製造が確定。
だが、ここから△3三角と打って後手が勝った将棋がA級で現れると、それ以降は△5四歩と突く将棋も見られるようになった。
対抗形
|
対抗形 |
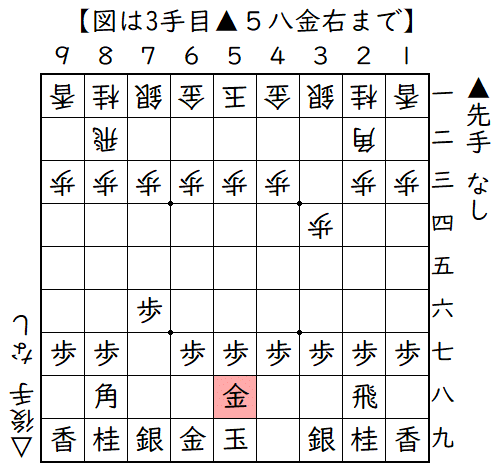
▲5八金右
2手目△3四歩に対する先手矢倉志向の手。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲5八金右△8四歩
以下▲6六歩△8五歩▲7七角△3二銀▲6七金△5四歩▲8八銀△3一角▲6八角のとき、△8六歩▲同歩△同角▲同角△同飛で後手が飛車先を交換できそうだが、その瞬間▲5三角と打たれて馬を作られる。
したがって▲6八角に△8六歩とは行けないため、△6二銀▲7七銀で先手は矢倉に出来る。
矢倉
|
矢倉 |
角換わり |
△3二金(△6二銀) |
▲7六歩△3四歩▲5八金右△3二金(△6二銀)
どうせ飛車先を交換できないのならば、と考えて飛車先を突かずに駒組みを進める。
矢倉、角換わり
|
矢倉 |
角換わり |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲5八金右△4四歩
後手振り飛車も見せる。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△3二飛(△3五歩) |
▲7六歩△3四歩▲5八金右△3二飛(△3五歩)
▲5八金右と上がっているので石田流の天敵・棒金の筋が消えているため、飛車を振るなら三間飛車が有力。
対抗形
|
対抗形 |
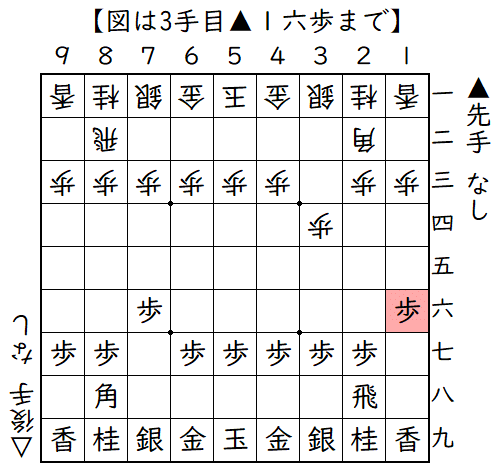
▲1六歩
藤井システムやゴキゲン中飛車によって完全に市民権を得た手。
|
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲1六歩△8四歩
▲5六歩と突いて先手ゴキゲン中飛車を目指せる。その他、▲6六歩で藤井システムなど、通常の振り飛車もある。先手振り飛車・後手居飛車の対抗形になるなら、▲1六歩は突いておいて損にならない。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲1六歩△4四歩
後手の作戦が矢倉か振り飛車に判明。ただし相振りになると▲1六歩は不利に働く可能性もある。
対抗形、矢倉、相振り飛車
|
対抗形 |
矢倉 |
相振り飛車 |
△1四歩 |
▲7六歩△3四歩▲1六歩△1四歩
1筋の突き合いがある形で先手が再び3手目を選ぶ。突き合いが得になる形を選びたい。
|
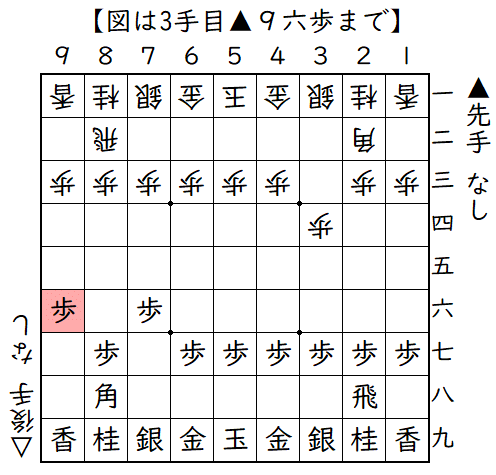
▲9六歩 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲9六歩△4四歩
▲7七角、▲7五歩などから相振り飛車になれば、▲9六歩は端攻めの権利となって現れてくる。相矢倉にしても、先手が急戦矢倉を狙えば▲9六歩は△9五桂を消しているなどのメリットがある。
対抗形、矢倉、相振り飛車
|
対抗形 |
矢倉 |
相振り飛車 |
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲9六歩△8四歩
後手が居飛車で角道を止めてこない場合は横歩取りまたは先手振り飛車。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
△9四歩 |
▲7六歩△3四歩▲9六歩△9四歩
9筋の突き合いがある形で先手が再び3手目を選ぶ。
|
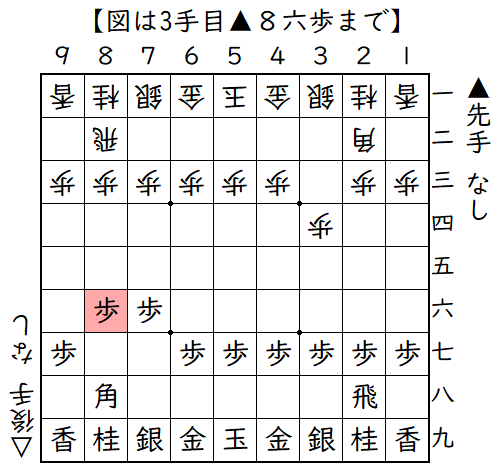
▲8六歩 |
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲8六歩△8四歩
先手角頭歩戦法。△8四歩には▲2二角成△同銀▲7七桂で8五を受ける。
角頭歩戦法、対抗形、相振り飛車
|
奇襲戦法 |
対抗形 |
居飛車力戦 |
△4四歩 |
▲7六歩△3四歩▲8六歩△4四歩
後手が角道を止め、上記の筋を防ぐ。現代では▲7七角~▲8八飛で一局の将棋。
対抗形、相振り飛車
|
対抗形 |
相振り飛車 |
居飛車力戦 |
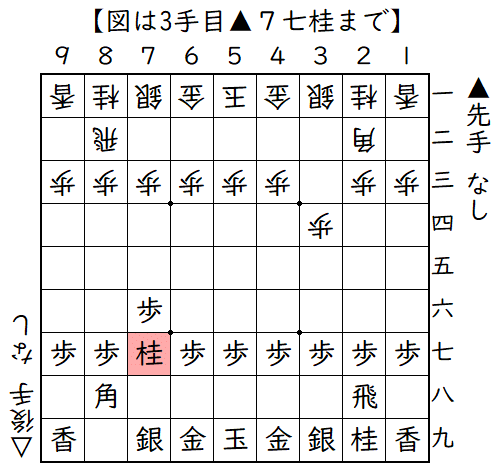
▲7七桂 |
△8四歩 |
▲7六歩△3四歩▲7七桂△8四歩
鬼殺し戦法。
以下△8四歩に▲6五桂と跳ね、
-
(1)△6二銀▲7五歩△6四歩▲2二角成△同銀▲5五角△3三銀▲6四角と進む奇襲戦法だ。
-
▲6五桂には△6二銀ではなく、
(2)△6二金が正解で、以下▲7五歩△6四歩▲2二角成△同銀▲5五角と同じように進んだときに△6三金と上がって受かる、というところまでが鬼殺しのお勉強。
鬼殺し
|
奇襲戦法 |
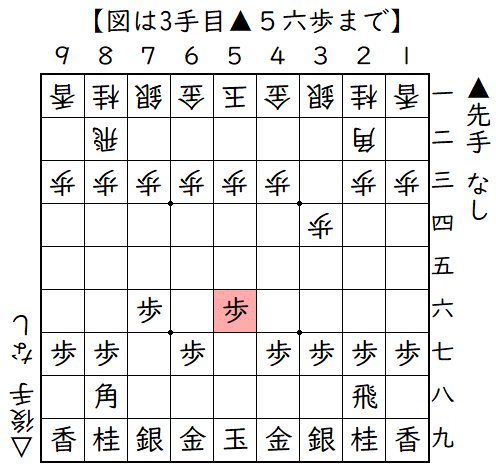
▲5六歩 |
△8八角成 |
▲7六歩△3四歩▲5六歩△8八角成
大野流向かい飛車と言われる戦法。△8八角成を▲同飛と取り、わざと△5七角から馬を作らせて指す。
対抗形
|
対抗形 |
1手目 |
2手目 |
3手目 |
4手目 |
戦型 |
▲7六歩 |
△8四歩 |
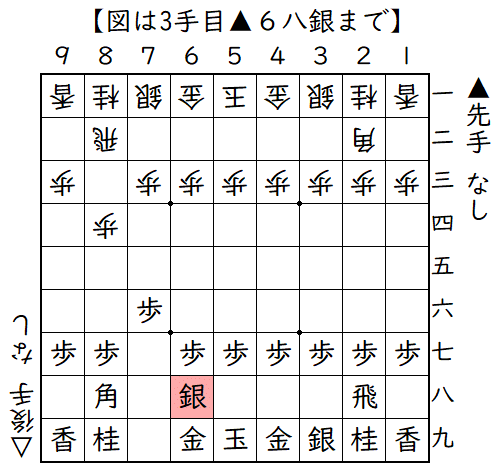
▲6八銀
矢倉の出だし。
|
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲6八銀△3四歩
基本的な矢倉の出だし。
5手目に、先手が▲6六歩か▲7七銀を選択する。その手次第で後手の急戦も変わってくる。具体的には、▲6六歩には右四間飛車、▲7七銀には矢倉中飛車。
その時々で流行り廃りがあり、1990年代から2010年代前半までは▲6六歩が主流だったが、その後新型の急戦が現れたことで▲6六歩は廃れ、▲7七銀が主流となっている。
矢倉、対抗形
|
矢倉 |
対抗形 |
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲6八銀△8五歩
後手が飛車先を決める順。
-
(1)▲7七銀と受ければ矢倉。
-
(2)▲7七角と上がると矢倉に組みづらくなるので、振り飛車模様。
矢倉、対抗形
|
矢倉 |
対抗形 |
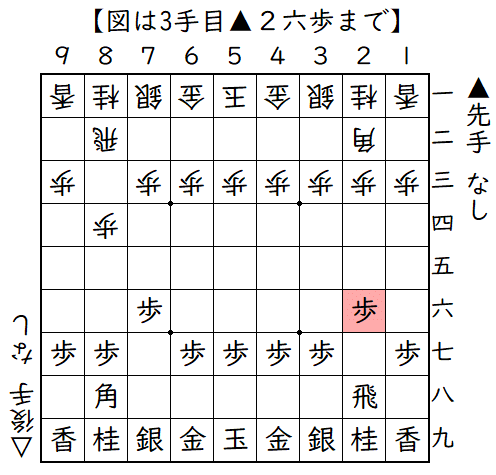
▲2六歩
角換わりの出だし。
|
△3二金 |
▲7六歩△8四歩▲2六歩△3二金
角換わりの出だし。
-
飛車先保留腰掛け銀を指す場合、
(1)▲7八金△8五歩▲7七角△3四歩▲8八銀(▲6八銀)。
-
▲2五歩型の場合は、
(2)▲2五歩△8五歩▲7七角△3四歩▲8八銀(▲6八銀)。
角換わり、矢倉
|
角換わり |
矢倉 |
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲2六歩△8五歩
角換わりの出だし。
-
飛車先保留腰掛け銀を指す場合、
(1)▲7七角△3四歩▲8八銀(▲6八銀)。
-
▲2五歩型の場合は、
(2)▲2五歩△3二金▲7七角△3四歩▲8八銀(▲6八銀)。
角換わり、矢倉
|
角換わり |
矢倉 |
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲2六歩△3四歩
▲7六歩△3四歩▲2六歩△8四歩と同じ局面。
|
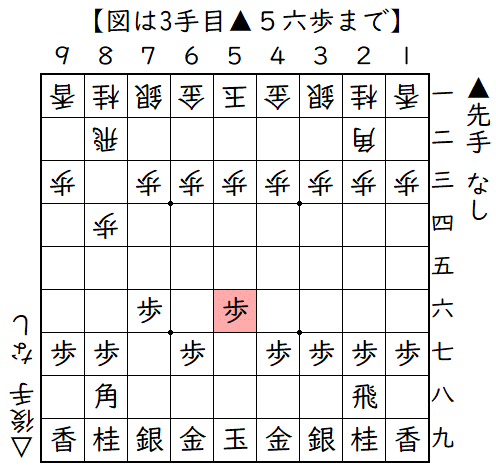
▲5六歩
2手目△8四歩には石田流が出来ないが、▲5六歩はそれに代わる先手振り飛車の有力手段。中飛車か、向かい飛車に振ることが多い。
|
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲5六歩△8五歩
以下▲7七角と上がり、
-
(1)△3四歩なら▲5五歩または▲5八飛で中飛車、
-
(2)△5四歩には▲5八飛の中飛車か、▲8八飛で升田流向かい飛車が多い。
対抗形
|
対抗形 |
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲5六歩△3四歩
▲5五歩または▲5八飛で中飛車。
対抗形
|
対抗形 |
△5四歩 |
▲7六歩△8四歩▲5六歩△5四歩
▲5八飛で中飛車にし、▲5五歩△同歩▲同角と突っかける筋が残る。ただし、その勝率は後手のほうが高い。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
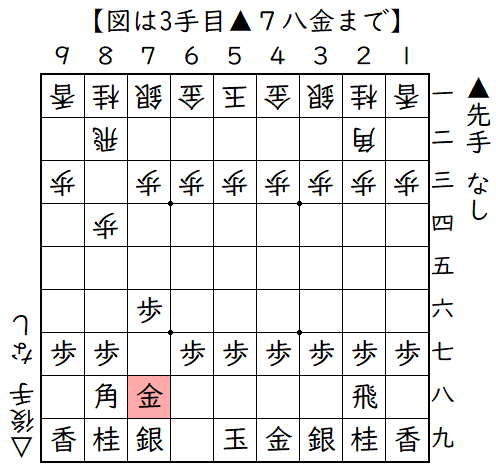
▲7八金
1990年代に入ってから増加した3手目。高田流とも言われる。
|
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲7八金△8五歩
以下▲7七角△3四歩▲8八銀ならば、飛車先不突で角換わりが出来る。他にも▲2六歩と突けば横歩取りにも持ち込めるので、まだ何にでも出来る出だしである。
|
戦型未確定 |
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲7八金△3四歩
▲7六歩△3四歩▲7八金△8四歩と同じ局面。
|
△3二金 |
▲7六歩△8四歩▲7八金△3二金
後手が様子を見た形。高田流は▲5六歩と突いて中飛車を目指せば作戦勝ちできるとする。実戦では▲6八銀か▲2六歩で、矢倉か角換わりを目指すことが多い。
戦型未確定
|
戦型未確定 |
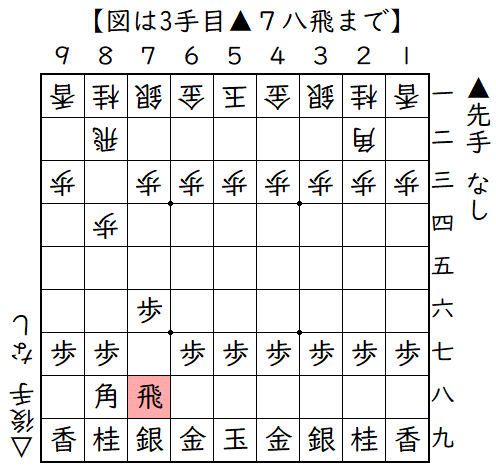 ▲7八飛
三間飛車の再評価によって増えている手順。
|
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲7八飛△8五歩
-
(1)▲7七角と上がり、△3四歩と突くのが一般的な進行。
-
(a)▲6六歩と突けばノーマル三間飛車。
-
角道を開けたまま指す方法が出てきており、
(b)▲4八玉、(c)▲6八銀、(d)▲7五歩が指されている。
-
(2)▲7七飛という奇策もある。後手が何もしてこなかったら▲7五歩~▲7六飛と突いて石田流にするのが狙い。
三間飛車
|
対抗形 |
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲7八飛△3四歩
-
(1)▲7五歩と突けば早石田の出だしに合流する。
-
(2)▲6六歩と止めればノーマル三間飛車。
-
(3)▲6八銀は角交換振り飛車を目指す手。
三間飛車
|
対抗形 |
▲6八飛
(▲7八飛)
(▲5八飛) |
|
▲7六歩△8四歩▲6八飛(▲7八飛、▲5八飛)
飛車を振っておく。
対抗形
|
対抗形 |
▲7五歩 |
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲7五歩△8五歩
石田流っぽいが、△8五歩を伸ばせば▲7七角と受けるしかなく、すんなり本組には出来ない。
対抗形、居飛車力戦
|
対抗形 |
居飛車力戦 |
▲7七角 |
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲7七角△3四歩
矢倉と思わせて先手がひねった順。角換わりに進むことが多いが、後手が角道を止めた場合は右四間飛車がある。
角換わり、対抗形、居飛車力戦
|
角換わり |
対抗形 |
居飛車力戦 |
▲6六歩 |
△3四歩 |
▲7六歩△8四歩▲6六歩△3四歩
相手の角道が止まっているのにわざわざ▲6六歩と突くのは、ほぼ振り飛車党と見ていいだろう。
対抗形
|
対抗形 |
矢倉 |
△8五歩 |
▲7六歩△8四歩▲6六歩△8五歩
▲7七角と受け、先手は矢倉にしづらい。
対抗形、矢倉
|
対抗形 |
矢倉 |
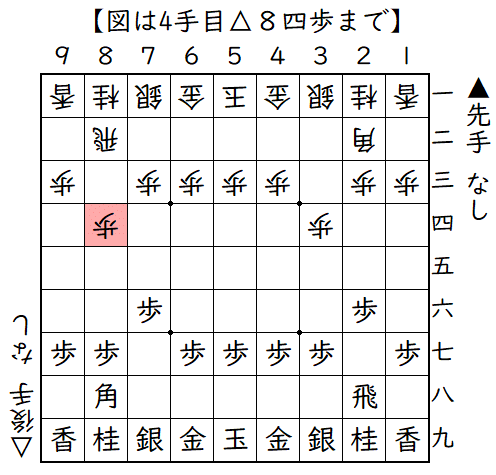 横歩取りの出だし。後手次第で一手損角換わりに進むこともある。
横歩取りの出だし。後手次第で一手損角換わりに進むこともある。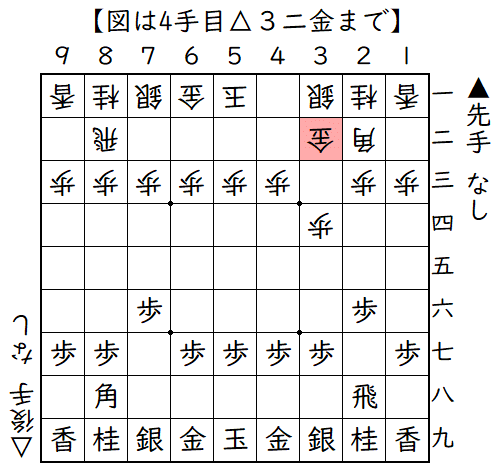 一手損角換わりの出だし。△8四歩型と飛車先不突型の選択ができる。また、横歩取りを誘うこともできる。
一手損角換わりの出だし。△8四歩型と飛車先不突型の選択ができる。また、横歩取りを誘うこともできる。
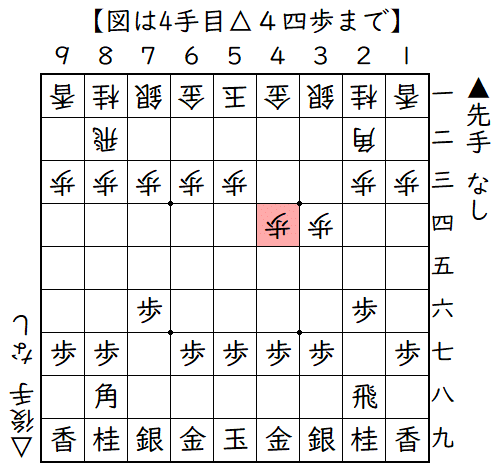 角道を止める穏便な指し方。後手は作戦を矢倉や雁木、または振り飛車に絞る。
角道を止める穏便な指し方。後手は作戦を矢倉や雁木、または振り飛車に絞る。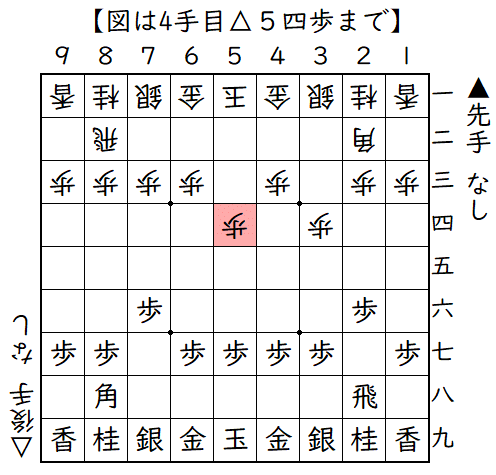
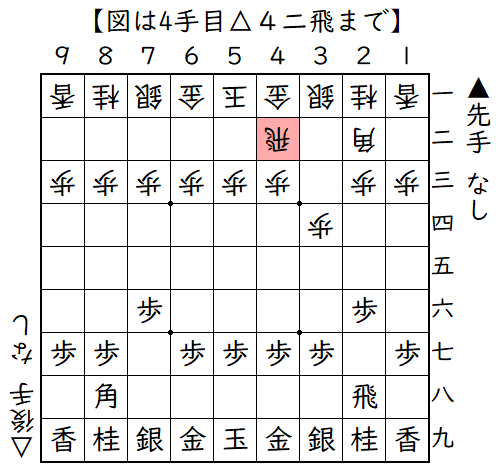 角交換四間飛車の出だし。
角交換四間飛車の出だし。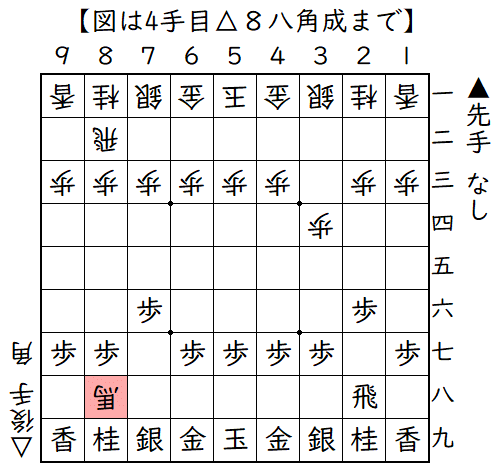 4手目にして角交換。
4手目にして角交換。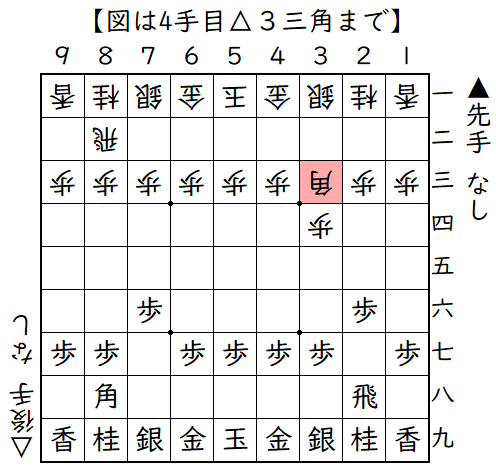 4手目△3三角戦法の出だし。
4手目△3三角戦法の出だし。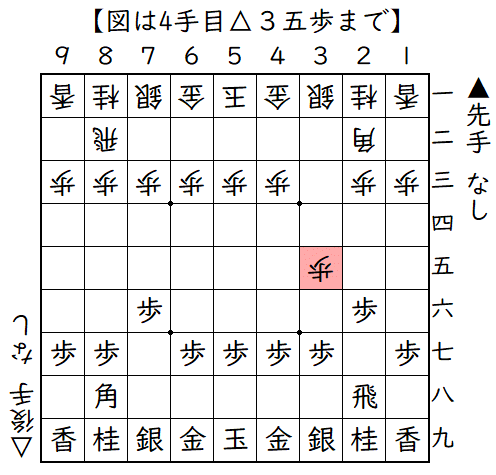 後手早石田の出だし。
後手早石田の出だし。
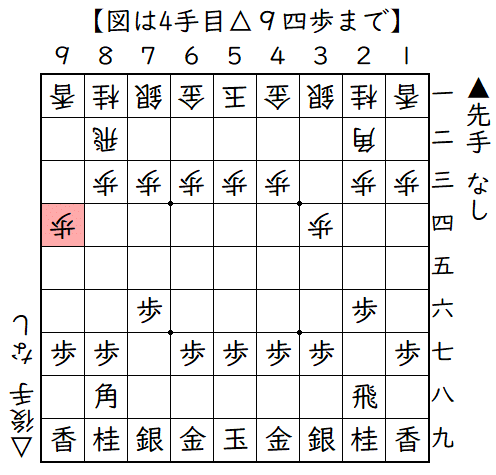 端歩で様子見。一手損角換わりや角交換振り飛車を狙っている。
端歩で様子見。一手損角換わりや角交換振り飛車を狙っている。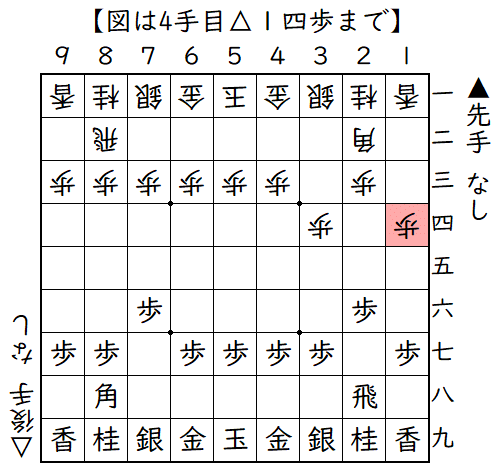 端の様子見。狙うとすれば一手損角換わり。
端の様子見。狙うとすれば一手損角換わり。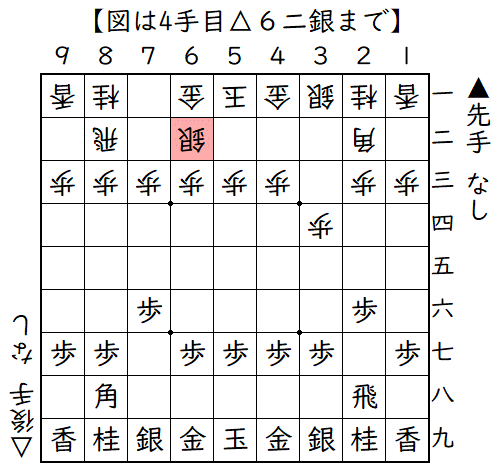 △6二銀は普通の手のように見えて、全然そうではない。
△6二銀は普通の手のように見えて、全然そうではない。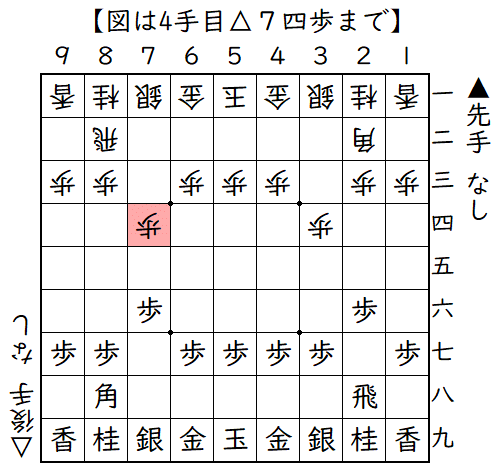 2手目△7四歩戦法の変形。
2手目△7四歩戦法の変形。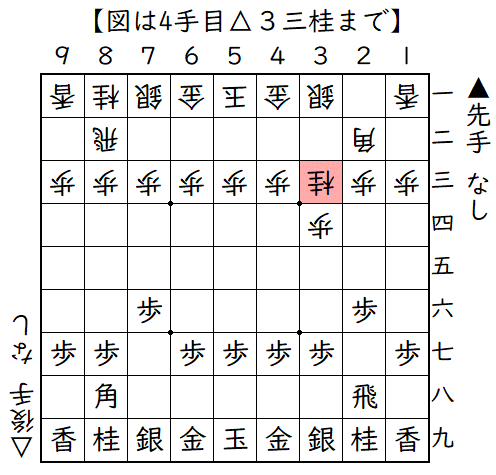 後手鬼殺し戦法。
後手鬼殺し戦法。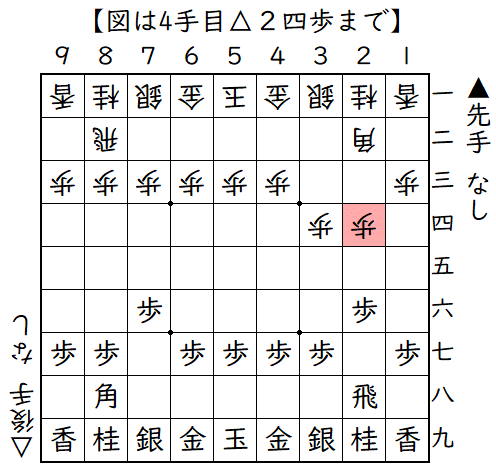 後手角頭歩戦法。
後手角頭歩戦法。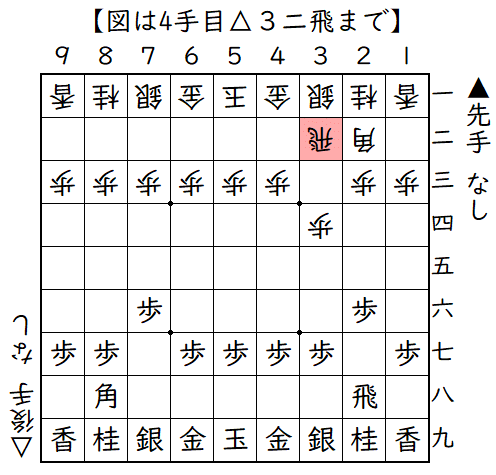 菅井流4手目△3二飛。
菅井流4手目△3二飛。